なぜ光秀は不可能を可能に?易経に学ぶ、逆境を覆す意思決定
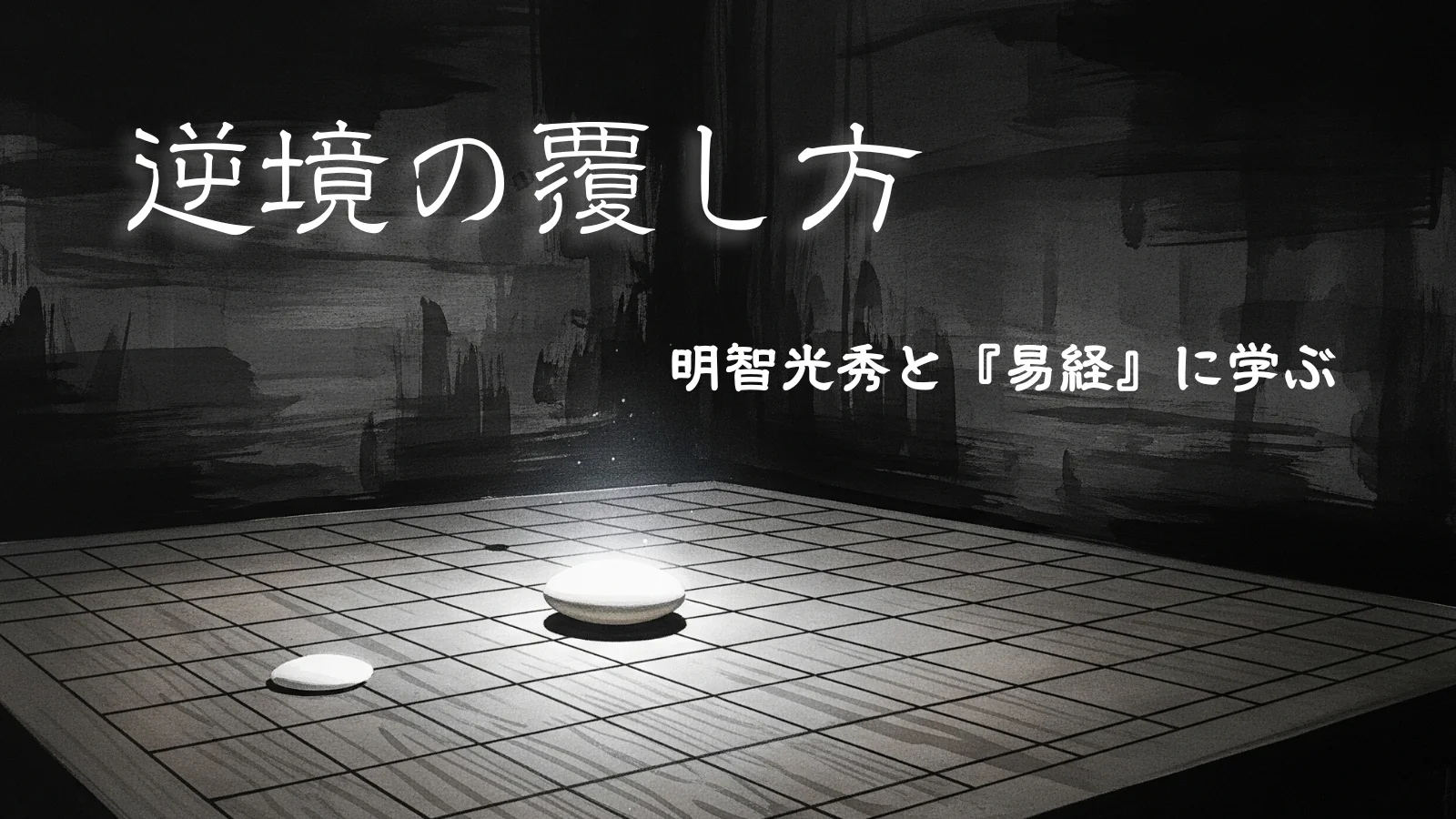
「着任早々、誰も手をつけたがらない『問題プロジェクト』を任されてしまった…」
あなたも経験があるのではないでしょうか。前任者が次々と失敗し、社内では「あれは無理だ」と囁かれる難題。PMである私にとって、これは悪夢のような、しかし何度も経験してきた光景です。
しかし、2500年前の中国で生まれた叡智は、時代と場所を超えて、困難な状況を打破するヒントを与えてくれます。その普遍的な知恵を、日本の戦国時代に見事に体現した一人の武将がいました。
1575年、明智光秀は織田信長から「丹波攻略」という、まさに「不可能なミッション」を命じられました。複雑に入り組んだ地形、統一されていない国人衆、そして何より、織田家の有力武将たちが次々と失敗してきた「鬼門」。
しかし光秀は、易経の「変化の道理」、老子の「柔よく剛を制す」、墨子の「実利主義」という三つの古典思想を組み合わせ、わずか4年でこの難題を解決してみせたのです。
データ分析と段階的アプローチ、そして現地との信頼構築—光秀の手法は、現代のプロジェクトマネジメントの教科書そのものでした。
織田家の鬼門、丹波国
天正3年(1575年)6月、安土城。
「光秀、そなたに丹波攻略を命ずる」
織田信長のその一言に、評定の間は静まり返りました。丹波—それは織田家にとって、まさに「鬼門」と呼ぶべき土地でした。
光秀は静かに頭を下げましたが、その胸中には複雑な感情が渦巻いていました。なぜ、自分なのか。柴田勝家、羽柴秀吉、滝川一益…そうそうたる武将たちがいる中で、なぜ、比較的新参の自分に、この困難極まりない任務が?
「承知いたしました」
そう答えた光秀の声は、いつもと変わらず落ち着いていました。しかし、彼は知っていたのです。これは試練であると同時に、大きな機会でもあることを。
孤独な知将の決意
坂本城に戻った光秀は、一人書斎に籠もりました。
丹波国—京都の西北に位置する山国。深い谷と険しい峠が複雑に入り組み、まるで天然の要塞のような地形。そこには波多野秀治、赤井直正といった、独立心の強い国人衆が割拠していました。
「力では解決できない…ならば、知恵で」
光秀は、愛読する『易経』『老子』『墨子』を机に並べました。幼い頃から学問を好み、諸国を放浪した若き日に身につけた教養。それが今、最大の武器となるはずでした。
最初の3ヶ月間、光秀は一切の軍事行動を起こしませんでした。代わりに、商人に変装させた忍びを送り込み、丹波の隅々まで調査させたのです。地形、城の配置、国人衆の性格、家臣団の構成、さらには彼らの趣味嗜好まで—。
「データなき戦は、闇夜を歩くが如し」
夜な夜な、光秀は集まってくる情報を整理し、頭の中で丹波の立体地図を構築していきました。
長い長い、見えない戦い
天正4年(1576年)春。ついに光秀は動き出しました。しかし、それは誰の目にも「戦」には見えませんでした。
小さな国人衆への接触、贈り物、宴席での語らい。光秀は、まるで茶人のように、一人一人と丁寧に関係を築いていきました。時には『論語』の一節を引用し、時には和歌を詠み交わし、相手の教養と誇りに敬意を示したのです。
「最初に降った者には最大の恩賞を。遅れる者ほど、得るものは少なくなる」
この巧妙な心理戦は、じわじわと効果を現し始めました。
しかし、天正5年(1577年)10月。光秀が信長の命令で播磨へ転戦している隙に、波多野秀治が離反。2年近い努力が、一瞬で崩れ去りました。
闇の中の一筋の光
亀山城の自室で、光秀は一人、天井を見つめていました。
「また、最初からか…」
疲労が濃い影となって、その顔に刻まれていました。しかし、ふと手に取った『易経』の一節が、彼の目を輝かせました。
「窮すれば変ず、変ずれば通ず」
そうだ、これは終わりではない。むしろ、新たな戦略への転換点なのだ。
天正6年(1578年)、光秀は全く異なるアプローチを開始しました。波多野秀治への直接攻撃ではなく、まず自らの娘を丹波の有力国人に嫁がせ、血縁による信頼の絆を築くことから始めたのです。同時に、その家臣団の中に、静かに、しかし確実に「疑念の種」を蒔き始めました。
「あなたの主君は、本当にあなたを評価しているのか?」 「織田家につけば、もっと大きな未来が待っているのでは?」
水が岩の隙間に浸透するように、光秀の言葉は、少しずつ、しかし確実に、敵の内部を侵食していきました。
勝利、そして不吉な予感
天正7年(1579年)6月。
八上城が陥落し、波多野秀治が降伏した瞬間、光秀は深い安堵と同時に、言いようのない虚しさを感じていました。
4年。まる4年もの歳月。その間に失ったものは、あまりにも大きかった。家臣たちの命、自身の健康、そして何より…信長との関係。
「光秀よ、よくやった。だが、なぜこれほど時間がかかった?」
信長の冷たい言葉が、今も耳に残っています。
丹波国主となった光秀。しかし、その瞳には、もはや喜びの色はありませんでした。知略を尽くし、人心を操り、ついに手に入れた勝利。しかし、その過程で、光秀は何か大切なものを失ってしまったような気がしてならなかったのです。その完璧すぎる知略は、時に人間的な感情の機微を置き去りにし、最も身近な家臣たちとの間にさえ、見えない壁を作っていました。
本能寺の変まで、あと3年...。
なぜ光秀だけが、古典の知恵を実践できたのか
明智光秀の丹波攻略は、単なる軍事的成功ではありません。それは、一人の教養人が、書物の中の抽象的な思想を、血なまぐさい戦国の現実に見事に「翻訳」してみせた、稀有な事例だったのです。
しかし、ここで問うべきは「光秀は古典をどう使ったか」ではなく、「なぜ光秀だけが、それを実践できたのか」ということでしょう。
易経との出会い:流浪の中で培われた「変化への感性」
光秀の前半生は謎に包まれていますが、諸国を流浪した経験があることは確かです。美濃を追われ、越前で朝倉氏に仕え、そして信長の下へ—。この「根無し草」としての経験こそが、光秀に易経の本質を体得させたのではないでしょうか。
易経『繋辞下伝』は説きます。
「窮すれば変ず、変ずれば通ず、通ずれば久し」
(行き詰まれば変化し、変化すれば道は開け、道が開ければ長続きする)
現代のスタートアップ用語で言う「ピボット(方向転換)」の思想そのものです。光秀は、この言葉を頭で理解したのではない。身をもって生き抜いてきたのです。
波多野の離反という挫折の夜、光秀が易経を手に取った時、そこに見たのは古い教訓ではなく、自分自身の人生そのものでした。「また変化の時が来た。これまでもそうだったように、今回も必ず道は開ける」—そう確信できたのは、流浪の経験があったからこそです。
他の武将たちは、生まれた土地で育ち、その土地を守る「定住の論理」で生きていました。しかし光秀は違った。変化こそが常態であり、適応こそが生存の鍵だと、骨の髄まで理解していたのです。
老子の実践:「外様」だからこそ可能だった柔軟性
老子『道徳経』第八章は述べています:
「上善は水の若し。水は善く万物を利して争わず」
(最上の善は水のようである。水はあらゆる物に恵みを与えながら、争うことがない)
なぜ光秀は、この「水の哲学」を実践できたのか。それは彼が織田家において「外様」であり、「よそ者」だったからです。
柴田勝家や丹羽長秀のような譜代の武将は、「織田家の威光」を背負って戦いました。力で押し、権威で従わせる—それが彼らの方法でした。しかし光秀には、頼るべき「家の威光」がありませんでした。
だからこそ、光秀は「水」になれたのです。相手の器に合わせて形を変え、隙間から浸透し、時には霧となって姿を消す。教養を示して文化人を魅了し、利益を語って商人を動かし、義理を説いて武士を説得する—この変幻自在な交渉術は、「根無し草」だった光秀だからこそ可能だったのです。
「私には押し付けるべき流儀がない。だから、あなたの流儀に合わせましょう」
この謙虚さは、計算ではなく、光秀の生き方そのものだったのです。
墨子への共鳴:「愛されなかった者」の普遍的愛
墨子『兼愛上』は説きます。
「人の国を視ること其の国を視るが若く、人の家を視ること其の家を視るが若く、人の身を視ること其の身を視るが若し」
(他人の国を自分の国のように、他人の家を自分の家のように、他人の身を自分の身のように思え)
なぜ光秀は、この一見非現実的な思想を、戦国の世で実践しようとしたのでしょうか。
その答えは、光秀自身が「愛されなかった者」だったからかもしれません。
流浪の身から這い上がり、常に「よそ者」として扱われ、どれだけ功績を挙げても信長からは冷遇される。光秀は、疎外される者の痛みを、誰よりも知っていました。
だからこそ、丹波の小領主たちに対して、差別なく接することができた。降伏した者を公平に扱い、民衆の生活を守ろうとした。それは戦略であると同時に、光秀の魂の叫びでもあったのです。
「私は、あなたたちを『敵』ではなく『人』として見ている」
この姿勢が、頑なだった丹波の人々の心を、少しずつ開いていったのです。
光と影:完璧な理性の孤独
しかし、ここに光秀の悲劇の種がありました。
古典の知恵を完璧に実践し、データと論理で戦略を組み立て、4年かけて不可能を可能にした光秀。しかし、その過程で、彼は致命的なものを失っていました。
人間としての素朴な感情の交流です。
すべてが計算され、すべてが戦略的で、すべてが合理的。光秀の完璧さは、周囲に畏怖を与えると同時に、ある種の不気味さも生み出していました。
「光秀殿は、何を考えているのか分からない」
この言葉が、やがて本能寺の変へとつながる疑念の連鎖を生むことになるのです。
あなたの「丹波攻略」を成功に導く5つのステップ
光秀の教訓を、明日から実践できる意思決定フレームワークに落とし込みましょう。
Step 1: 徹底的な現状分析(易経の「観」)
「問題プロジェクト」を引き受けたら、まず3週間は動かない。ステークホルダーマップを作成し、過去の失敗要因を全て洗い出す。特に「なぜ前任者は失敗したのか」を感情を排して分析することが重要。
Step 2: 段階的アプローチの設計(易経の「漸」)
一気に解決しようとしない。「Quick Win」を積み重ねる計画を立てる。最初の1ヶ月で達成可能な小さな成功を3つ設定し、チームの士気を高める。
Step 3: 柔軟な関係構築(老子の「水」)
対立ではなく協調を。反対派の中でも「説得可能な人」から順にアプローチ。その人の「利益」は何かを理解し、Win-Winの提案を準備する。
Step 4: 実利の明確化(墨子の「利」)
全ての施策に明確なROIを設定。「なぜこれをやるのか」を数字で説明できるようにする。感情論ではなく、データで勝負する。
Step 5: 撤退ラインの設定(リスク管理)
光秀が陥った「やりすぎ」を避けるため、予め撤退条件を設定。投入リソースの上限、期限、そして「これ以上は危険」というレッドラインを明確にする。ここまでやってもダメなら撤退する」という基準がないまま突き進んだプロジェクトが、どれだけ多くのリソースと人の心を破壊したか、私はこの目で見てきました。光秀の悲劇は、他人事ではありません。
警告:完璧主義の罠
光秀の失敗から学ぶべき最大の教訓—完璧な戦略は、時に人間性を失わせる。80%の成功で満足し、残り20%は「人間関係」に投資すること。
まとめ
明智光秀の丹波攻略は、易経の「変化の道理」、老子の「水の哲学」、墨子の「実利主義」を見事に融合させた、意思決定の傑作でした。
データに基づく分析、段階的な実行、柔軟な戦略転換—これらは全て、現代のプロジェクトマネジメントにそのまま応用できる普遍的な原理です。
しかし同時に、過度な合理性がもたらす人間関係の軋轢という「影」も、光秀は教えてくれています。
あなたが次に「不可能なミッション」を任された時、まず深呼吸をして、3週間の調査期間を設定してください。そして小さな成功から始め、水のように柔軟に、しかし着実に目標に向かって進んでください。
ただし、忘れないでください。最後に人を動かすのは、論理ではなく信頼だということを。私も、完璧な計画に固執するあまり、チームメンバーの心を置き去りにしてしまった苦い経験があります。
2500年の叡智と、戦国の知将の経験が、あなたの決断を確かな成功へと導いてくれるはずです。
この記事をシェア
古典の知恵を現代に活かす戦略思考を、あなたの仲間にも伝えませんか?
著者
歳三
(ITコンサルタント / 歴史戦略研究家)この記事は一般人の学習記録であり、専門家による助言ではありません。 実践の際は自己責任で判断してください。
関連記事
参考文献
- 『易経』高田真治・後藤基巳訳、岩波文庫、1969年
- 『老子』蜂屋邦夫訳注、岩波文庫、2008年
- 『墨子』山田琢訳注、新釈漢文大系、明治書院、1975年
- 『明智光秀と本能寺の変』藤田達生著、筑摩書房、2019年
- 『明智光秀の生涯』小和田哲男著、新人物往来社、2014年
- 『丹波攻略戦—明智光秀の苦闘』渡邊大門著、吉川弘文館、2020年
- 『戦国武将の意思決定』小和田哲男著、中公新書、2018年